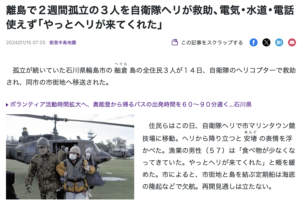2017年1月、秋田県のナマハゲなど、10件の奇祭が、「来訪神:仮面・仮装の神々」としてユネスコの無形文化遺産に登録されましたが、登録されたお祭りのうち、鹿児島の離島のお祭り3件とその周辺の離島の奇祭も合わせてご紹介します。
目次
「来訪神:仮面・仮装の神々」の構成行事
ちなみに、ユネスコの無形文化遺産に登録された構成行事はこの10件です。
- 「甑島のトシドン(鹿児島県薩摩川内市)」
- 「男鹿のナマハゲ(秋田県男鹿市)」
- 「能登のアマメハギ(石川県輪島市・能登町)」
- 「宮古島のパーントゥ(沖縄県宮古島市)」
- 「遊佐の小正月行事(山形県遊佐町)」
- 「米川の水かぶり(宮城県登米市)」
- 「見島のカセドリ(佐賀県佐賀市)」
- 「吉浜のスネカ(岩手県大船渡市)」
- 「薩摩硫黄島のメンドン(鹿児島県三島村)」
- 「悪石島のボゼ(鹿児島県十島村)」
鹿児島県の来訪神
甑島、硫黄島、悪石島の来訪神のお祭りは、仮面をつけた仮装した姿の神が来訪する行事として、ユネスコ文化遺産に登録されました。どの神様もユーモラスな姿で、興味深いです。
他にも、竹島、黒島、種子島、加計呂麻島、与論島の奇祭も紹介します。

甑島のトシドン(薩摩川市)
甑島のトシドンは、毎年12月31日(大晦日)の夜に、家々を訪れ、新しい年を迎える子どもの健康と幸せを願う神様です。シュロの皮やソテツの葉で飾り付け、鼻の長い恐ろしい顔をしています。

トシドンは天空や高い山や岩の上から、首のない馬に乗ってくると言われており、3歳~8歳の子どもがいる家々を数人で訪れ、子どもたちの日ごろの良いところを褒めたり、諭したり、歌を歌わすなどします。そして、最後に年餅と呼ばれる大きな餅を与えて去っていきます。トシドンからもらう年餅を食べないと年をとることができないといわれています。
甑島以外でも、屋久島の宮之浦,種子島の野木之平,安城の平山など数集落でも同じような伝統があります。
薩摩硫黄島のメンドン(鹿児島郡三島村)

薩摩硫黄島のメンドンは、八朔の行事として、旧暦の8月1日・2日に現れ、土地と人々の邪気を祓う役割を担っています。
熊野神社前の広場で、若者が八朔太鼓踊を奉納するところから始まります。硫黄島の八朔踊は、背中に八幡を背負い、胸に太鼓を抱いて、この太鼓を叩きながら踊ります。
この踊りを眺めていると、突如拝殿の裏からメンドンが走ってきて乱入します。そして踊り手達の周りを3周し、去っていきます。

1体のメンドンが去っていくと、次々とメンドンが走って乱入してきて踊り手の邪魔をしたり、観客たちを「スッベン木」と呼ばれる枝(柴)で叩いて回ります。叩かれると、邪気が祓われると言われています。
メンドンは、神社を出入りしながら、翌日の夜中まで島内の各所に出現します。
翌日には、「叩き出し」が始まり、メンドンが先頭になって太鼓踊をしながら島内を一周します。海岸につくと、邪気の叩き出しが始まるので、観光するのであれば、海岸沿いで見るのがおすすめです。
島内をめぐり終わったあとは、神社に戻って、踊で奉納し、「花開き」と呼ばれる会があり、お祭りが終わります。
悪石島のボゼ(鹿児島郡十島村)
鹿児島の離島群島である吐噶喇(トカラ)列島の中の一島である悪石島では、毎年旧暦の7月16日にボゼのお祭りが開催されます。

バリのような南国を思わせる ビジュアルの姿の神様です。頭からは大きな耳のような形のものが伸び、その根本にはお椀のような目があり、大きく口を開けています。頭部は、赤土色と黒色の縦縞模様で、体はビロウの葉で覆い、その上から赤土をまぶしています。
手には、「ボゼマラ」や「マラ棒」と呼ばれる男性器を模した長い杖を持ちます。
盆踊り最終日に現れ,死霊臭がただよう盆から,人々を新たなる生の世界に蘇らせる役目を負った仮面神です。

日本中にさまざまな形態の神や鬼、化け物がありますが、そのいずれの姿とも似ていないことから、“南方”からの伝来を思わせますが、この姿となったのは、むしろ、現在の「鬼」のビジュアルが定型化する前の人々が持っていた、素朴な「異形観」と、島にある物で造形するというブリコラージュがこのような形の神を作り上げたのではないでしょうか。
お盆の最終日である旧暦7月16日の夕方ごろ、3体のボゼが集落の墓地に隣接しているテラと呼ばれる場所から、呼び太鼓の音に合わせて広場に出現し、ボゼマラの先端につけた赤土を観客に擦り付けようと追い回します。
この泥には、邪気を払う力があるとされ、女性には子宝に恵まれるご利益もあるとされています。
太鼓のリズムがゆっくりになってくると、ボゼは体を揺らすように踊り始め、リズムの急変で再び暴れ出し、広場を去っていきます。

ボゼの去ったあとは、また盆踊りが始まり、深夜まで踊りと飲食が続きます。
お祭りにボゼが出現しない吐噶喇列島の島々でも、「ポジェ」と呼ばれる鬼の話があり、ボゼは、もともとは吐噶喇列島共通の仮面神だったと考えられます。
竹島のタカメン
竹島では、旧暦八月一日、二日に行われる「八朔踊り」があり、その時に高さ1mにもなる大きな面をつけたタカメンと呼ばれる神様が現れます。大きな耳のような飾りがあり、三角帽のように尖った形をしています。目はつり目で、のこぎり状の歯も特徴的です。どのお面も、色紙で色彩豊かな彩色がされています。
タカメンという呼び名の由来は面が「高く尖っているから」や、「鷹を模しているから」ともいわれています。また、同時に現れる小型の面はカズラメンとも呼ばれています。

タカメンは、村人の鉦や太鼓の音に合わせて踊り、手にした柴で村人を叩いて厄を祓い、繁栄をおこすといわれています。
黒島のオニメン
毎年9月1日に、黒島大里八朔踊りが行われ、その踊りの中で、オニメンと呼ばれる竹と紙で作ったお面を使う踊りを面踊りと呼んでいます。お面を被り、全身をシュロの皮で覆ったオニメンは、夕方頃から現れた始めます。
面は様々で、かっぱやひょうたんのような面もあり、決められた模様や様式はないようです。腰にひょうたんをぶら下げ、すりこぎとしゃもじを打ち鳴らしながら隊列を組んで、子孫繁栄、五穀の実り(豊穣・生産)を祈る踊りを踊ります。
加計呂麻島の諸鈍シバヤ
加計呂麻島にある諸鈍集落は、源平の戦いに敗れ、落ちのびてきた平資盛(たいらのすけもり)が居城を築いた場所と伝えられています。諸鈍集落の入口には、大屯(おおちょん)神社があり、平資盛を祀っています。
「シバヤ」は一般に「芝居」がなまったものといわれており、平資盛が土地の人との交流を深めるために伝えたのが始まりといわれています。
諸鈍シバヤは、旧暦の9月9日に開催される「大屯神社祭」で披露されています。大屯神社祭の特徴は、全て男性で構成されていることで、彼らはカビディラとよばれる紙のお面を着け、頭には陣笠風の紙笠をかぶります。

お気に入りのカビディラを探すのも楽しいかもしれません。
与論島の朝伊奈
与論島で室町時代から踊り継がれているという十五夜踊りは、旧暦3月,8月,10月の十五夜に、雨乞いの祈りとして踊られます。踊りは、一番組と二番組で構成されており、一番組は室町時代の狂言を源流とした本土風のもので、二番組は琉球の流れを汲む舞踊です。

一番組は、白装束に黒足袋で踊ることが多いですが、二番組は、紺に染めた装束に幅の広い帯を締め、後ろにテイザージと呼ばれる手ぬぐいを下げます。そして、シュパやシファと呼ばれる長いスカーフのようなもので顔と頭を覆っています。長さが40cmもある朝伊奈面を被る演目もあります。日の丸の描かれた扇子を持って踊ることもあります。
**************************
離島は、本当とは文化が違うことが多いです。なので、離島には変わったお祭りがあり、とても面白いです。旅行の際には、混むかもしれませんが、お祭りの時期を狙っていくと、いつもの旅行とは全く違う雰囲気が楽しめますよ。
離島の奇祭に興味を持った方は、こちらの本が、とても参考になります。鹿児島で日本の民俗学を研究している下野敏見著の南九州の伝統文化についてをまとめた2巻立てのシリーズです。
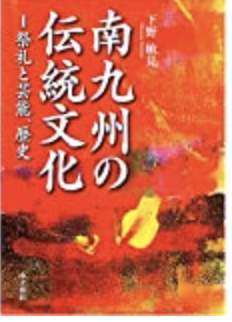 | 南九州の伝統文化〈1〉祭礼と芸能、歴史 (鹿児島県の伝統文化シリーズ) 新品価格 ¥5,134から |
 | 南九州の伝統文化〈2〉民具と民俗、研究 (鹿児島県の伝統文化シリーズ) 新品価格¥5,134から |